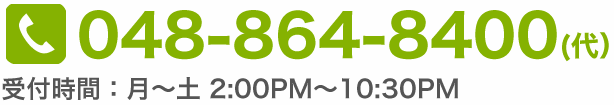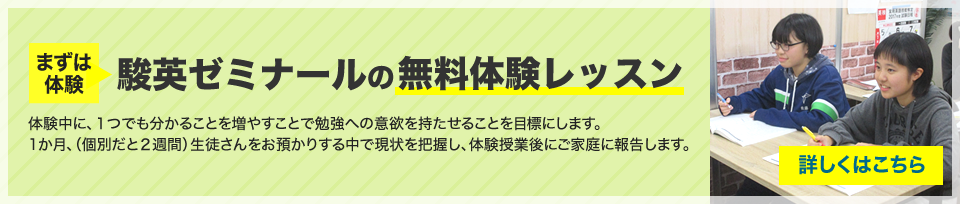先生ブログ


お悩み相談1
2024年12月15日 17:19
Q 小4小6年生の男の子兄弟の親ですが、外で問題行動を起こしますし、宿題もやりません。
自分の好きなことしかやらないし、嫌な科目からは逃げてばかりです。このこ達を変えることは出来るのでしょうか?
現状まったく見通しがつきません。
これは先日 体験授業に来てもらったご家庭のお母さまからのクエスチョンです。
外で問題行動を起こし、面倒なことから逃げる、好きなことしかしない
とても健全で元気な兄弟ですよね笑
エネルギーを良い方向に向けられるようにしていきましょう
A としては、 ①ルールを守る場所を作ってゆく。 ことと ②家庭内でも最低限のルールは作って
守れなかったん場合の処置も考えましょう。 ということをお伝えしました。
男の子ですし、元気で やんちゃなのは良いことですよね。 エネルギーが足りないより多い方が良いです。
ただ小さいうちは 自分の感情だけ優先、 周りとの約束とか、周りへの気使いができない、社会を舐めている
そういった部分が大きくなると とてもとてもお母様が大変な状況にはなりますね笑 周りのお友達や大人もそうですね。ですので、そこを変えていくためにの方法を
いっこずつお伝えしますと
①ルールを守る場所を作る
これはすごく大事ですね。うちは塾なので、勉強を通して最低限のルールを守らないといけない状況を作ります。
これは「塾」でなくてもいいです。習い事で、サッカーでも野球でも チームスポーツの中でゲームのルール、チームのルールを守る中での「達成感」「成長の実感」を体感する中で、
「大変だったり嫌なことがあっても、やっていくと出来ることがある」
これを体験から 感じること、学ぶこと、これが大事です。
言葉や理屈で小学生のことを説得する、変えていくことは基本「できない」と思ってもらっていいです。
ですので駿英においてはまず「やった状態を作る」ここを重視しています。
宿題をやってこない⇒ 「じゃあ今日は居残ってやってもらうけど、なぜやれなかったと思う?」
「家であと忙しくてやれなかった」
「だったら必ずやる日をつくったほうがいいから来週は月曜日に塾に宿題を遣りに来てもらうことにしよう」
そうすると 翌週は宿題が「やれている」状況になります。ここで初めて「ほめること」も出来ますし
宿題をやっている分「忘れていない」ので本日の授業も 「わかります」よね。
この時に 「塾に来ても宿題うちの子は出来ないかも」というお母さんもいますが、 「やっても出来ない」のか
「やっていないだけ」なのか。ここをはっきりさせるためにも 一度「塾で宿題をやらせる」ことが重要です。
しかも感覚としては8割9割の子は 誘惑がなく、先生に見張られている中での宿題は「出来ます」
こうして「やれた」経験があると、子どもの方から「塾でやるとやれるから、自習に行ってきます」と自分から
授業がない日に来塾するようになったりしますね。 「自発的」に「環境を選択する」ことが出来たらこれはもう
「大きな成長」ですよね。宿題も 嫌な科目も「塾」に来てやるようになればやれるような体験が積み重なっていくと、
段々問題行動も減っていきます。 問題行動は基本的には「学校や習い事」などの子どもの世界の中での
「不足している達成感」を 皆がやらない「問題行動」で達成するための エネルギー発散である場合がほとんどです。
※もちろん ご家庭での家族との関係性が 大きなウェイトを占める場合もありますが、だいぶ個人情報なので割愛させてもらいます
ですのでまとめると
「ルールを守り 何かを達成できる環境の中で、ほめたり成長を実感させられる行動基準をつくってゆく」
ということです。 ルールを守らないんですうちの子は、 というお母様もいると思いますが、 そこは理屈ではなく
「ルールを守らせる指導者」の下でやってもらう、ということですね。 お友達感覚ではなく、ピシりと やらせられる
指導者を探してください。ということです。駿英に関しましては、そこは 任せていただければ、 必ず変えていきますの で ご安心ください
②家庭内で最低限のルールを守る
これに関しては 先によくないルールをお伝えします
例1 テストの点数で95点以上を取ること
例2 宿題を夕方5時までに終わらせないとゲームをやれない
例3 このテキストをいついつまでに終わらせる
これ何がよくないかというと、 「能力」にかかわるルールだからです。
野球チームで例えるなら、 子供たちの成長を促すために
例1 ホームランは必ず 1本は打つこと
例2 ノーミスでノックを受けきらない場合、バッティング練習はさせません
例3 素振り10000本を 来週までにやりなさい
このちーむで 子供の心の成長や 自信や、 自主性が 作られていくのか?ということです。
作られないですよね。 不必要な劣等感や あきらめは身につくかもしれません。
最低限のルールというのは「姿勢」や「マナー」に関わるものであるべきだと思っています。
ここの部分はなにかを「継続して」「積み上げて」「成長を実感して」「自分に自信を持てるように」
してゆくための 必要不可欠な土台の部分になります。
ご家庭にお願いするとすれば
「決められた日に塾には送り出してください」
「休みたい、ばあいは自分で電話をさせて下さい」
「宿題ができない場合に一緒に解いたり教えたりはせず、正々堂々と塾に自分でもって行きなさい」
これくらいです。
なのでご家庭でルールを決める場合も
「社会的に、道徳的に必要なルール」という部分を作り、そこを破るのは許さない姿勢を見せていけば
子供も変わります。 大人が毅然とした態度で、ここは許さないと線引きをしてあげることが、一番大事なこどもへの
「愛情表現」であると駿英では考えています。
細かくご相談してもらっていいので、一緒に子どもたちの 気持ちの成長人間的成長を作っていけば、
必ず勉強面の成長はその上に乗っかってきます。
とお伝えさせていただきました。
次回ブログでは、 具体的な子供たちの成長例をご紹介させていただきます。