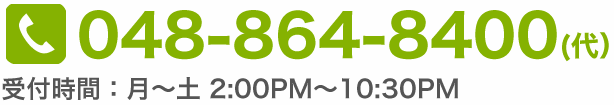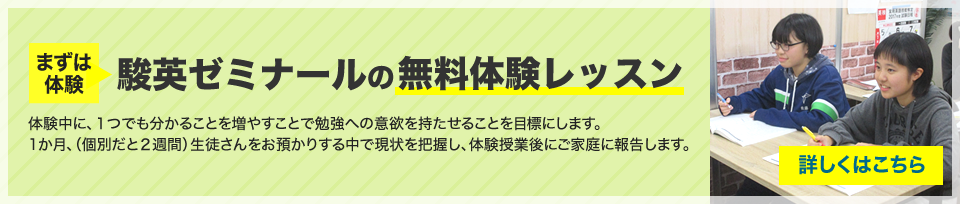先生ブログ


お悩み相談2 例1 M君の話(中学1年生~高校受験~大学受験)
2024年12月31日 13:12
こんにちは 連投になりますが
前回の お悩み相談1 ⇒ https://www.sunei-seminar.com/archives/12720
の続きです。
子どもの習慣 能力ではなく 道徳的な、自分を律するための習慣を 身に着けてゆくことで、成績も上がる
出来るようになってゆくというパターンを 今回と次回以降で2パターンの子を紹介しようと思います。
まず一人目は 今はもう大学一年生の子ですが、昨年まで駿英にいた子です。
結論から言うと、彼は昨年の大学受験、第一志望も含めて 全勝しました。厳密にいうと総合型推薦での受験では
第一志望に落ちましたが、 その後の一般受験の方で見事リベンジを果たし、本人が希望する大学、受験した大学はすべて合格しました。
では 模試の偏差値が余裕で A判定が出ていたのか?というと、最後までC判定すら出ていません。しかし合格をすべて勝ち取りましたが、こういったタイプの合格に駿英の先生たちは「驚きません」
そもそも初めて駿英に来た時の彼の成績は2が並び、中学校の授業を受けていても分からないことだらけ、というスタートでした。しかし最終的に彼が合格した大学、学部は、埼玉県の上位の公立高校の子でも不合格する子が多数いる大学、学部でした。
しかし、中学1年生のころから彼のことは見てきましたが、本人の成長、そしてご家庭のご協力(これは一般的にいう教育パパ、ママの行動の「逆」をお願いしています) をみていれば、我々は驚きません。 高校の先生たちは結果に驚いていたようですが、 大事なことは「継続性」と「目標設定」の仕方が間違っていなければ、結果は出るという分かりやすい例ですので、 彼の話をご紹介したいと思います。
生徒例 その1 M君
彼が駿英に来たのは中1の夏ごろでした。学校の授業についていけない、英語、数学ともに点数としては30点台で
とくに英語は授業で何を言っているのか分からないということでしたが、無料体験で様子を見せてもらったところ、むしろもっとまずいのは数学でした。 小学5年生で習う 分数計算は崩壊状態で、公倍数も公約数も抜けている状態でした。
もともと小学校のころから駿英に通っているお友達から聞いて体験授業に来たのですが、彼らと同じクラスで中1の内容をやっても学校と同じく授業についていけない状態ですとお伝えし、個別指導で小学生の内容からスタートになりました。
クラスでやれるようになったら戻りましょうということで、英語も中1の最初から、数学は小5に内容からです。
最初のころは「宿題はできませんでした」「家に忘れました」 「家から出るときに野良猫から襲われました」など
よくわからない理由をつけて 宿題をやってこなかったり、遅刻をしており 担当の講師からは叱られ、居残りをさせられる日々が続きました。
※一般的には個別指導の塾の場合、宿題をやってこなくても叱られず、先生と一緒にやってもらえたりします。子どもの満足度は高いです。しかしこれだといつまでたっても「大人が横にいないと勉強できない子ども」から抜け出せなくなります
しかし、まずは 「家だとやらない」「やれない」ということを自覚してもらい、 塾の宿題と学校の課題を「塾にやりに来る」習慣をつけてもらいました。 全員駿英の生徒は 授業日以外に「自習日」を設定し、毎週来てもらいます
※ちなみにこのM君は中1の2学期より木曜日の自習日を設定しました。授業がなくてもこの日には自習に来るという習慣を、高3の3月、大学受験が終わった後まで継続し続けることになります。
しかし中1時点の彼には週1回の自習だけでは 塾の宿題も終えられません。内容は小5の内容ですが、家だとTVを見る。動画を見る、ゲームをしてしまいます。 ですので担当講師と約束をし 授業日2日以外に 月曜木曜と自習に来ることになりました。 数学は火曜日 英語は水曜日 なので、全部で週4日塾に毎週来る 「習慣」をまずは作りました。
部活動は「陸上部」でのちに副部長にもなりましたので、まじめに部活には出ていましたが、何度か挫折や壁にぶつかり
「転部」をほのめかしたことがありましたが、 塾での面談においては基本は絶対に「継続して頑張ろう」と伝えました。
ひとつ何かを 乗り越えてやり切ることが すべてにつながるからです。逆に一つでも「逃げ癖」がついてしまった子を伸ばすようにするのは「至難の業」になっていきます。 勉強と関係ないように聞こえるかもしれませんが、実はこういったところから「心の癖」はついてしまいますので、駿英ゼミナールでは子どもの「勉強以外のヒアリング」の機会を
多く作り、子どもが「伸びやすい」心の習慣、心の環境を作ってゆくことも講師間で共有し、計画を立てていきます。
M君の変化は 中2の1学期中間ごろに出てきます。
習慣が定着してきてから、まず 学校の提出物を事前に仕上げることが出来るようになり、内申から2が消えました
その後 段々と小学生の算数が埋まり、中1の内容をやっていく中で、 学校の授業が「わかる」状態に追いつき始めました。 目標の50点には届きませんでしたが、ひどいときには20点台だった 数学が40点台後半になり、
英語も 40点に乗っかるようになりました。彼の素直さ、性格の良さ これがとても強みになったことは確かですが
一番は 彼は逃げない、やり切る ということを部活動や駿英の生活の中で身に着けていったことが大きかったです。一番大事な成長ポイントです。
さらに駿英では毎学期末に 文化センターや市民センターの会議室を借り「キャリア教育」を行います
そこで将来のライフスタイルや仕事、 そのための大学学部、資格 そしてそのための高校選び、そのために中学でどういう成績を取るかという風な「上流から考える」機会を 毎学期作っています(中1~高3まで)
そこで彼が自分の長所や、好きなことを考えたときに はじめは困っている人たちの為にNPO団体で困っている子どもたちを支える仕事をしたい、そのために社会学や教育学を学びたいというところから 大学を探していました。
(のちに目標は変わっていくのですが、考え知識が増える中で目標が変わっていくことは健全な成長ととらえています。)
そう考えると今のままではだめだということになり 陸上部としての目標、勉強面での目標を設定し、そのためには
授業後にも残って勉強するということを自分で決めるようになります。
しかしもちろん人間、子どもですので 約束は破られます笑 そのたび我々の出番です。 サボった分はいつ来るのか、決めなさい。 逃がさず、習慣を「守らせる」ことで継続したことが自信になります。
ここまで見ていただいても お気付きのように、基本は 本人たちに決めてもらっています。 我々は決めません。決める機会だけは必ず作ります。
でも決めたことを守れない時、逃げてしまうとき、人間なのであります。ここで逃がしてしまうと「計画立ててもどうせやれないから、計画も立てない」子になります。
だからこそ なんとしても 守らせるための外圧 これは必要です。やり切らせる、継続させる。ここは子供の気分には任せません。
そうした中で、だんだんと習慣が安定してくる中で 本人の「工夫」が可能になってきます。
量が担保されて 初めて質が変わってきます。M君は 苦手な英語から学校提出物を終わらせて、一番本人は楽な社会や副教科の方を順番は後ろにすることで、テスト前に近付くにつれて出来る科目に取り組めるようにして行きました。
本人はテストに向けてだんだんとモチベーションが上がるようになったと喜んでいました。
そして中3になるころには 国語や理科社会はクラスでやり、
数学もクラスでやれるようになりました。英語だけはまだしばらく 個別指導でという形で 中3を迎えました。
そして高校調べも行ってゆく中で、 公立高校、私立高校ともに志望校が夏前には決まり、 夏の講習、合宿、北辰テストと受けてゆく中で 第一志望の学校も 「自分で決める」「親にお願いする」というプロセスで 見事合格を勝ち取りましたが、 本人が「自立してゆく」プロセスの中での成長があれば 彼に限らず良い結果は出てきます。
高校受験も頑張りましたが、 高校受験の先の目標も 皆と同じように 作ることが出来た
彼の本当の成長は 高校生活に入ってからでした。
次回(高校生活の中での目標設定と、成長)をお伝えしますが
中学生活の中で彼が 手にした一番の財産は「自分で目標を決めた」という実績です。
ご両親のご協力なくしてこの体験は手に入りませんでした。ご両親、もしくはどちらかの親御様がすべての保護者会に参加していただき、M君の為に
「勉強面には一切口を出さない」「親としてはこちらの学校の方がと思うが、本人の志望動機を尊重してくれた」ことにより
かれは高校受験を通して 「自分で目標を決め」「周りの協力を得ながら」「やり切った」経験を手に入れられました。
彼からすると「自立」を認められた、応援された という財産。これが成長してゆくための土台になります。
逆に子供のことを思うあまりに 親の意向を押し付けてしまう。そこに従ってしまう関係は、合格を手にしたとしても
本人の「自信」にはつながりません。 逆に、自分でモチベーションを作れない心の癖がついてしまいます。 自信をつけさせたい、自信を持ってほしい、自分で考えてほしい。そう願うご家庭、親御さん 皆さんそうだと思います。しかし悪気があるわけではないですが、押し付けてしまうことで、逆に 自信の持てない、外からの目標設定待ちの子になってしまう。皮肉なことです。こういった子は究極的には勝負弱い子になります。これは避けないといけません。
メジャーリーガーになりなさい、と押し付けられていたら、大谷翔平ですら、野球はやめてしまったかもしれません。
だからこそ大事なことは 初めての受験で「自立体験」をすることです。ここを経験し、なおかつここで歩みをとめずに駿英に通い続けた子たちは そのごの大学受験でも 彼のような勝利、獲得を手にしています。勝負強い子になっていきます。駿英のご家庭に関しましては、M君のおうちに限らず、ここのご協力していただける御家庭ばかりで 感謝しております。 今後のおこさまの成長もご期待ください。
さて、M君に戻りますと、彼の自立体験、そして高校での成長において、大事になっていたポイントは 「相対的」ではなく「絶対的な」動機を作ることでした。高校生であれば、さらにそこが大事であり、駿英以外の同級生の子たちと比べたときの「強み」になります。
NPOで働くと言っていた
彼の将来の目標がどう変わってゆくのか、そして
そのための土台を中学時代に手にしたM君の高校生活での成長に関しては 次回書かせ頂きます。
高校生活の彼のスタートは 駿英で行った「大学生との共同ワーク」から始まります。
次回また お会いしましょう。 それでは